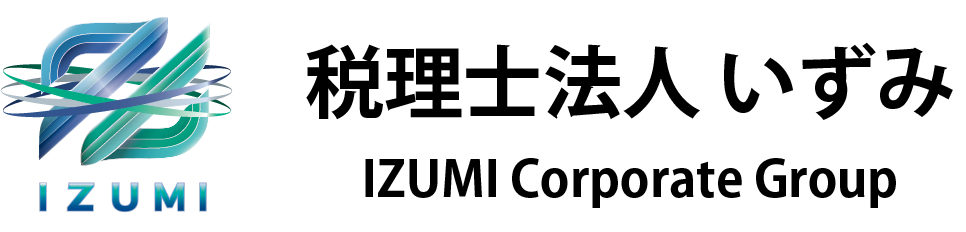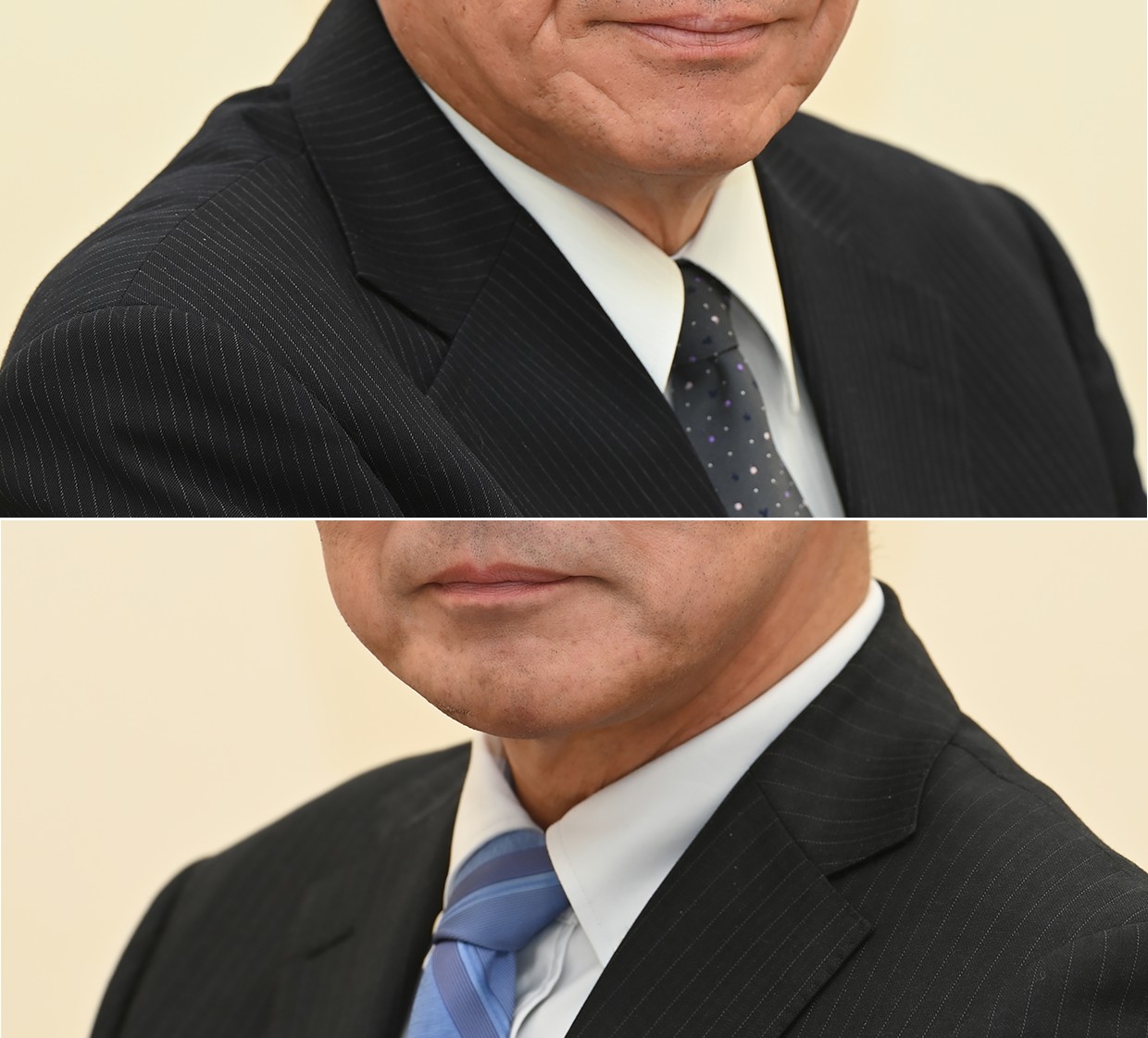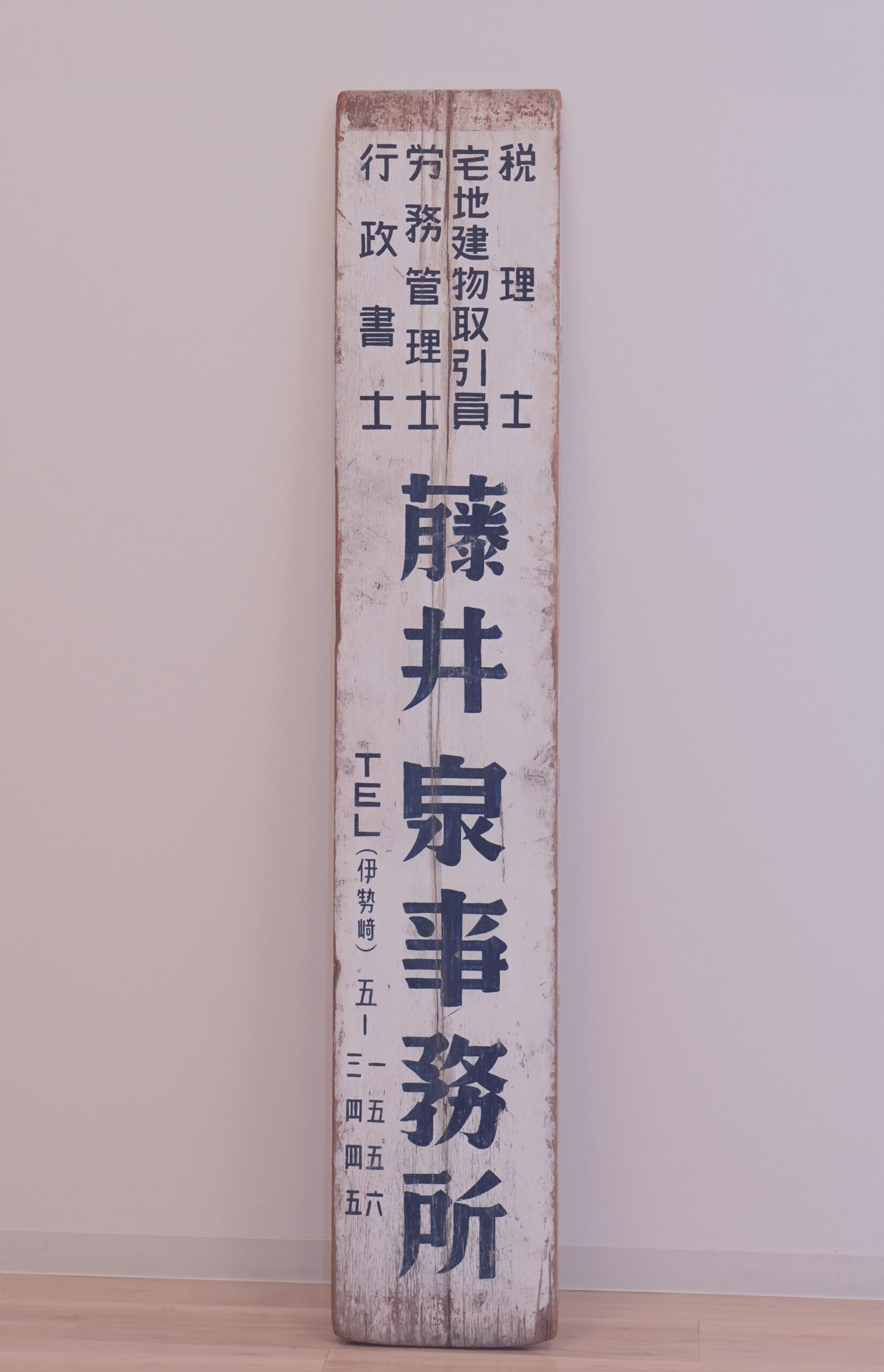税務調査の流れ

元税務調査官ならではの「調査官目線」での対応
税務調査の実務を熟知しているからこそ、調査官がどこを見て、何を疑うかを的確に予測できます。
調査官の視点を理解した上で、事前準備から対応戦略まで、無駄のないサポートを提供します。

税務署から調査通知が届いたら、まずは冷静な初動対応が重要です。
元税務調査官の税理士として、通知内容を精査し、調査の目的や対象期間、調査官の意図を読み取ります。

税務調査通知が届いたら、まず冷静に内容を確認します。調査対象や意図を読み取り、事前準備と税理士との連携が鍵です。
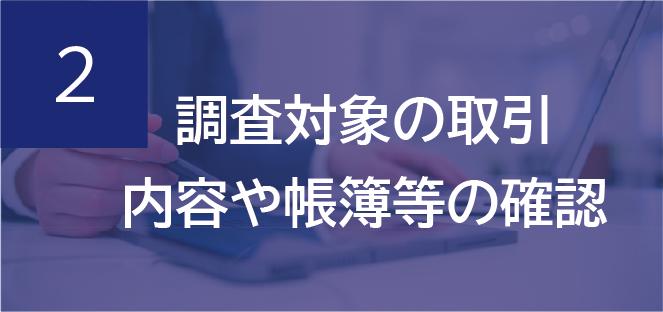
税務調査では、対象取引の帳簿や証憑の整合性が重要です。事前に内容を精査し、説明できる状態にしておくことが信頼につながります。

調査官は数値の違和感に敏感です。過去事例からも、帳簿の整合性がリスク回避のポイントです。
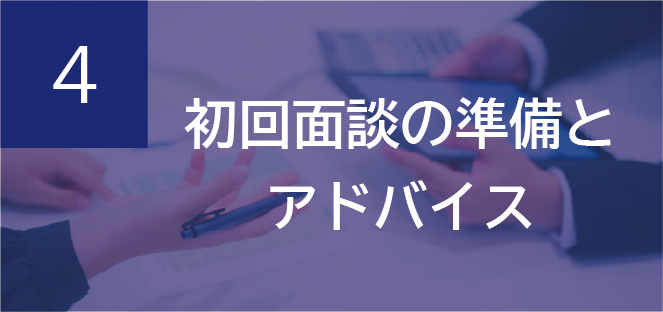
初回面談は調査官との信頼構築の場です。事前に帳簿を整理し、想定問答を準備して、冷静に対応できるようにサポートします。
初動を誤ると、調査が長期化したり、不要な指摘を受ける可能性があります。
そのため、通知を受けた段階での専門的な判断が非常に重要です。

税務調査では、帳簿・領収書・請求書・契約書など多くの資料が求められます。
元調査官の視点から、どの資料が重要か、どのように整理すべきかを的確にアドバイスします。
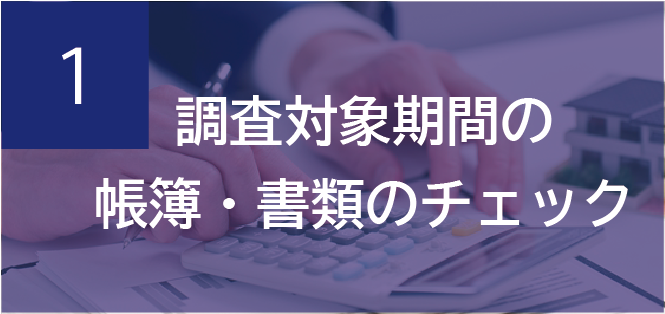
調査対象期間の帳簿や証憑は、整合性と保存状況が重要です。抜けや不備がないか事前に丁寧に確認します。
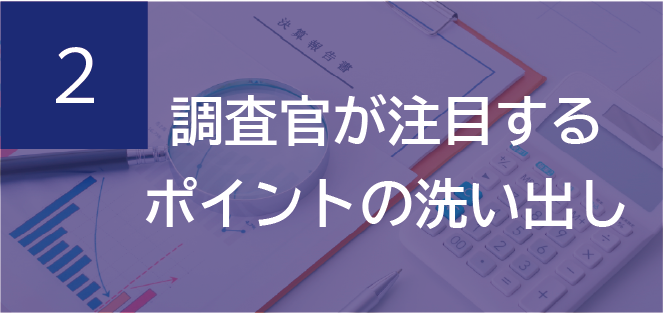
調査官は異常値や不自然な取引に注目します。業種特性や過去申告との比較から、指摘されやすい箇所を事前に洗い出しておくことが重要です。
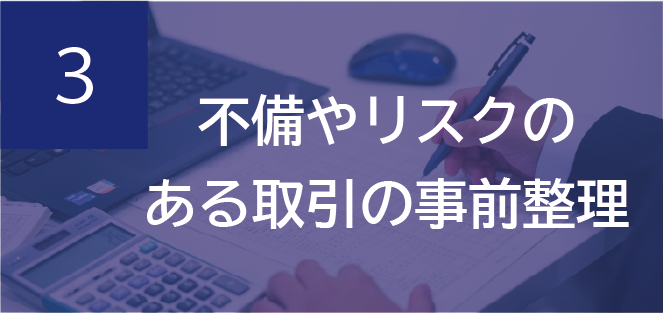
申告内容に不備やリスクがある取引は、事前に洗い出して整理をします。説明できる準備が、調査時の安心につながります。
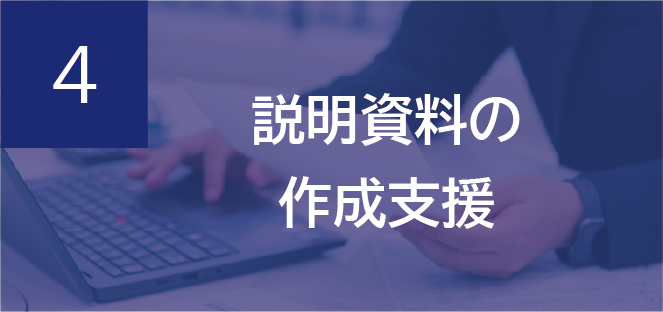
調査官への説明資料は、取引の背景や経緯を整理して、客観的かつ簡潔にまとめることがポイントです。事前準備で対応力が大きく変わります。
「見せ方」や「説明の仕方」ひとつで、調査官の印象や判断が大きく変わることがあります。
そのため、資料の準備は単なる整理ではなく、戦略的な対応が求められます。

調査当日は、税務署の調査官が実際に事務所や店舗に臨場し、帳簿や取引内容等の原始記録を確認します。
その場での対応が、調査の結果に直結するため、専門家の立会いが非常に有効です。

調査官とのやり取りは、冷静かつ丁寧な対応が基本です。税理士が同席し、必要に応じて専門的な説明や記録の補助を行うことで、調査が円滑に進みます。
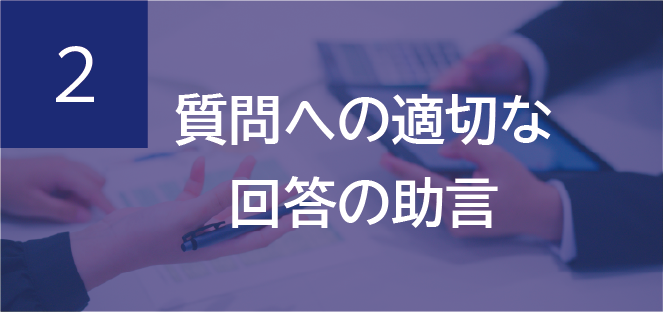
調査官の質問には、事実に基づき簡潔かつ正確に回答をしましょう。曖昧な返答は誤解を招くため、必要に応じて税理士が助言します。
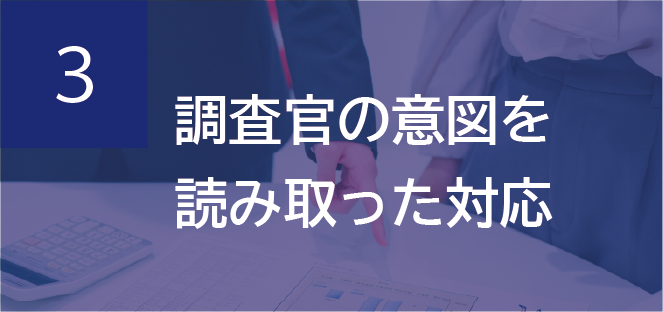
調査官の質問や資料要求の背景には、確認したいポイントがあります。意図を読み取り、的確な資料と説明で対応することが信頼につながります。
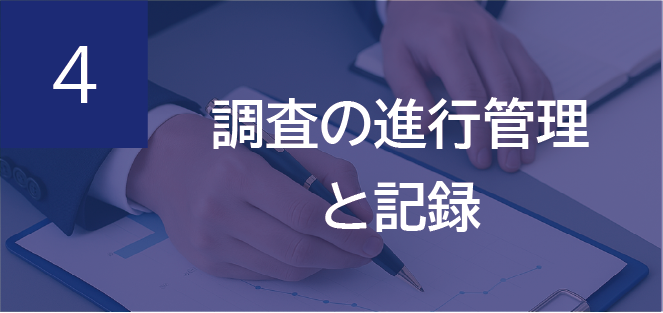
調査の進行状況は、面談内容や資料提出履歴を記録しながら管理をします。後日の確認や対応方針の整理に役立ちます。
調査官とのやり取りに慣れていない方でも、税理士が同席することで安心して対応できます。
また、調査官の質問の背景を読み取り、誤解を防ぐ説明を行うことができます。
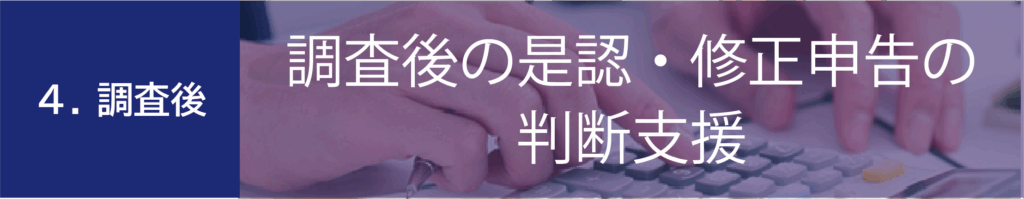
調査が終わった後は、税務署からの指摘内容に対して、是認(問題なし)か、修正申告(訂正)を行うかの判断が必要です。
この判断は、今後の税務リスクにも関わるため、慎重な対応が求められます。
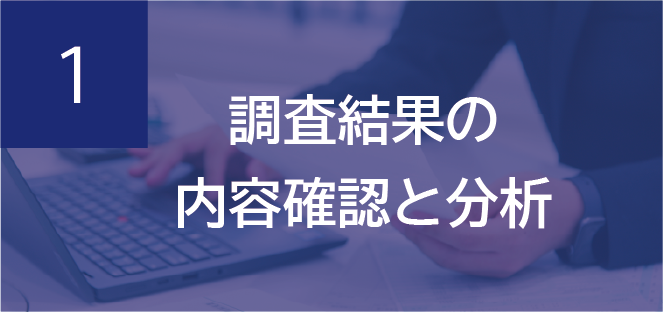
調査結果は指摘事項の根拠や影響を丁寧に確認し、事実関係を整理した上で対応方針を検討することが重要です。

申告内容に誤りが確認された場合は、修正申告が必要です。指摘の根拠や金額の影響を分析して判断します。
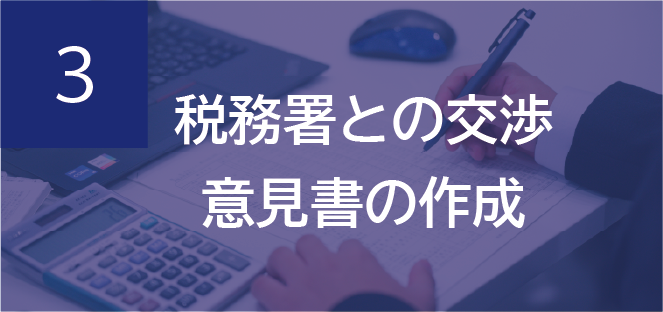
税務署との交渉では、事実と根拠を整理した冷静な対応が重要です。見解の相違がある場合は、専門的な意見書で納税者の立場を明確に示すことが有効です。
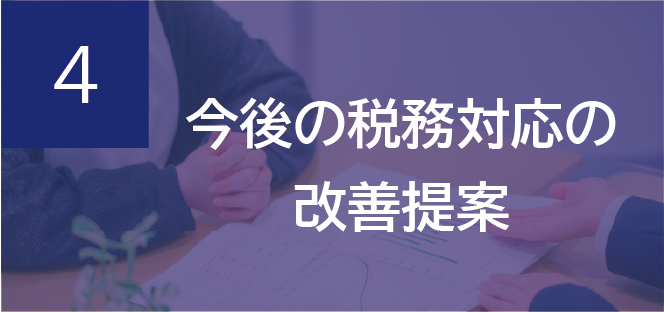
調査結果を踏まえ、帳簿管理や経費処理の見直しをします。再発防止のための社内ルール整備と、税理士との定期的なレビューが有効です。
調査後の対応を誤ると、追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。
元調査官としての経験を活かし、中立・公正な立場で明確に税務署等の国税当局に意見をいう姿勢を貫き、納税者の納得のいく形で調査を終えられるようサポートします。